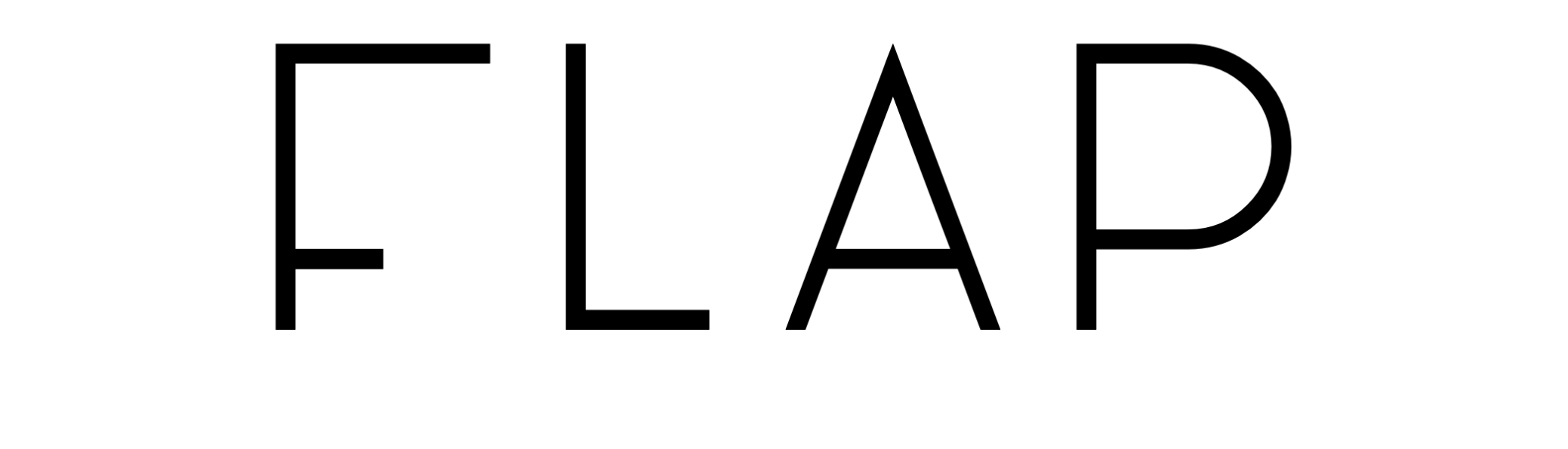MITとGeorgia Techに研究留学した科学大生達が当時を振り返ってみた

交換留学を考えている人の中には、「向こうの大学で研究できるのかな?」「研究室ってどうやって見つけるの?」と疑問に思っている人も多いのではないでしょうか?
実は、私たちも最初は同じように悩んでいました。大学のプログラムには「この講義が履修できます」とか「この寮に住めます」といった情報はあるけど、「研究室に入るには?」という情報は意外と少なかったんです。
そこで今回は、私たちが交換留学で研究室を見つけた方法や、実際に研究生活がどうだったのかをお話ししようと思います。これから留学を考えている人の参考になれば嬉しいです!!

なめちゃん:無料で見れたカレッジフットボールの試合。観客の人数が多過ぎて、キャンパス内にある会場だとは思えないぐらい!笑
スピーカー紹介(留学当時)
なめちゃん:物質理工学院材料系B4。
あーちゃん:工学院電気電子系B4。

なめちゃん:研究室のあった建物。機械工学科と材料工学科のほとんどの研究室が同じ建物の中にあった。
対談
なめちゃん:私は、2024年8月から12月にかけて、アメリカのジョージア州アトランタにあるジョージア工科大学に留学していました。あーちゃんはどこに留学してたの?
あーちゃん:私はマサチューセッツ州ケンブリッジにあるマサチューセッツ工科大学(MIT)に留学していました。授業も2つ取っていたけど、研究もしていました。なめちゃんも研究してたんだよね、どうやって見つけたの?
なめちゃん:研究先を探すときは、ジョージア工科大学の材料工学科(自分の所属した学部)で研究室の一覧が載っているページから、興味のある研究をしている先生を見つけたよ!それぞれの研究室には、ラボのホームページがあったり、研究室紹介の動画があったから、それを参考にした。そして、一番興味のある先生にメールを送ったよ!あーちゃんも同じ感じで、研究室を見つけた?
あーちゃん:私もネットで「MIT+研究テーマ」で調べて出てきた研究室にメールを送ったから、同じ感じ。メールにはCVと特課研の内容を英語でA4の紙2枚にまとめたものを添付してみた。メールの文面はUROPのホームページに例があったから、それを参考にしたかな。UROP事務所の人には、先生からなかなかメールが帰ってこなかったり、一つの枠をたくさんの学生で争ったりして大変だと聞いていたけど、私の場合は3日後くらいにPhDの学生からメールが帰ってきてスムーズに決まったから良かった。先生から反応が返ってこなかったら、居室を訪問してみたり、授業終わりに待ち伏せしてみるのも手だと言われていたけど、そこまでせずには済んだ笑。なめちゃんはスムーズに決まった?
なめちゃん:自分の場合は、早めにどの研究室で研究できるか、研究テーマを知りたかったから、8月中旬にアメリカに渡航したけど、5月中旬に先生にメールを送ったよ。自分もCVと特課研の内容をまとめたパワーポイントを添付した。一番最初に送ったときから2週間何も返信が来なかったから、「I sent you a similar email a few weeks ago, but wanted to follow up in case you missed it.(数週間前に似たメールを送ったのですが、万が一先生が見逃してた時のために、もう一度メールを送ります)」みたいな感じで、少し催促メールを送ったね笑 そうしたら、次の日には快く受け入れてくれる旨のメールをもらえて、とても嬉しかったのを覚えているよ!メールの内容の中に、「あなたの研究室テーマのこれに興味があって、実際自分の大学ではこういうことをしています」って書き入れて、少しでもやる気があることを強調するように気を付けたよ。あーちゃんは、渡航した後に研究室の先生にメールを送ったの?あと実際に研究室が決定する前に、先生と面談をして本当にそこで研究をしたいかを確かめたりした?

あーちゃん:MITといえば!のGreat Dome。ドームの下は24時間開いている図書館
あーちゃん:渡航前に研究室を決めておけば、事前に準備もできるし渡航後すぐに研究を始められるから良いよね!実は私がメールを送ったのは渡航後なんだよね。なめちゃんはB3後期で研究室に早期配属してたと思うんだけど、私は普通にB4の4月に配属されたから、5月には研究に関して書けることが何もなかった笑。だから研究室探しはプログラムに受かってからちょこちょこやってたけど、諸々書き始めたのは8月下旬に特課研の発表が終わって渡航してから。渡航前に交換留学生向けのUROPのオリエンテーションがあったんだけど、事務局の人が「だいたいみんな渡航してから始める」って言ってたから、それで安心してたのもある。
UROPはメールを送った後に先生か学生と面接をするっていう流れで採用・不採用が決まるんだけど、私の場合はメールの時点で受け入れてもらえることがほぼ確定してて、直接会って話した時も研究に必要な手続きに関して説明してもらう感じだったから、面接というよりはオリエンテーションに近かったかも?特にマイナスの意味で気になる点とかはなかったから、そのままそこで研究させてもらうことにしたよ。
なめちゃん:なるほどね!実際、自分の周りでもほとんどは渡航後に研究室の先生にコンタクトしてた人も多かったから、別に渡航前にしないと困るってわけではなさそうだね~。実際、研究室の所属が決まってからは、どういう感じで研究テーマを決めたり、研究を進めていったの?
あーちゃん:研究テーマはPhDの学生に割り当ててもらったかな。アメリカの大学院(博士課程)に進学するつもりがあるかどうか聞かれて、もしそうなら実績(論文)があった方がいいからってことで論文になりそうなテーマを提案してくれた。週に1回メンターのPhD学生とのミーティングがあって、それ以外は個人で研究を進めてた。学期末には研究室で毎週やってる全体ミーティングで発表したよ。なめちゃんはどう?
なめちゃん:渡航の1,2週間前ぐらいに、研究先の先生から、4つぐらい研究テーマの候補を挙げて、そこから自由に選んでいいよっていうメールをもらったよ。それで、一番興味がありそうなテーマを選んだら快諾してもらえた。あと、渡航した後、先生と初めて話したときに、「pythonはやったことある?」っていきなり聞かれて、「なんとなくやったことあります」って返したら、追加でプロジェクトを投げてもらえた!どちらも、自分1人で進めるタイプの研究だったけど、毎週水曜日に先生とディスカッションする時間をもらえてたから、わからないこととかはすぐに聞けて良かったね。自分も、学期末の全体ミーティングで、学期中の研究で何をしたかっていうプレゼンをした!この留学での研究の中で、特に苦労したことはある?
あーちゃん:分野は東工大でやってた特課研と同じだったけど、テーマは違っていたから知らないことが多くて最初は大変で、色々教えてもらってた。あと、東工大では実験寄りの研究だったけど、MITでは理論寄りの研究をしていて、Pythonで色々コードを書かないといけないのが初心者の私には大変だったかな。もちろん最後のプレゼンも大変だった!

あーちゃん:春休み中に開講されてた大人気のdeep learning の授業。最終回にはTシャツをもらった
なめちゃん:自分も同じ感じだった!分野は大体同じなんだけど、研究の対象が少し違ったり、今まではやったことなかったような、Pythonでコードを書いて結果を分析する、っていうこともやったりしたから、色々調べたり、先生や周りの人に聞いたりしたね。自分も、最後のプレゼンは緊張したけど、そこまで失敗せず終われたから良かった!留学に行く前まで、自分の英語力でアメリカの大学の先生と研究の話ができるのか不安を抱えていたし、これから留学に行こうとしようとしている学生も同じことを考えているかもしれないけど、英語力に関する心配はなかった?やっぱり、TOEFLで100点とか基準点を超えていたとしても、自分の専門分野についてしっかり議論するのは難しくなかった?
あーちゃん:難しかった!東工大では、英語を使うのは主に論文を読むときだけだったから、いざ喋るとなると専門用語がすぐ出てこないことがよくあったよ。ネイティブスピーカーではない人たちの訛りのある発音とか、ネイティブの速さとかで、そもそも相手の発言が一回で聞き取れないなんてこともあった。最終発表は1時間弱かかったけど、3分の1くらいは私がひたすら「何て?」って聞き返す時間になってたと思う笑。TOEFL100点っていうのはあくまで最低条件なんだなって実感したよ。
なめちゃん:やっぱりそうだよね…。自分も、先生とのミーティングで研究進捗の報告をして、それについての議論をするときには、詰まってしまうことはよくあったね。なんだかんだ先生はとても優しくて、話すのに時間がかかっても、しっかり理解しようとしてくれたから、楽しみながら研究ができた気がする。とは言っても、これからもそういう優しい人ばかりに頼ってられないから、もっと研究に関することも英語で議論できるようにしないといけないなって実感できたね。それじゃあ最後に、今後アメリカへの交換留学や研究留学をしたい人に対して、伝えたいこととかあったりする?
あーちゃん:研究以外にも色々不安なこととか大変なこともあったけど、留学は研究の面でも生活の面でも成長できた貴重な機会だったと感じているよ。日本に帰国した後もMITでやっていた研究は続けていて、成果を論文にまとめる流れにもなってきてる。語学要件とか準備しないといけないことはたくさんあるけど、得られるものはたくさんあるから、少しでも興味があれば挑戦してみてほしい!
なめちゃん:確かにそうだね。留学先では、研究だけでなく、生活面や自分の内面の成長にもつながるから、色んな人におすすめしたいね!金銭的に心配になる人もいるかもしれないけど、調べてみると様々な奨学金があるから、積極的に使ってほしい。ぜひ、留学に少しでも興味がある人は、どんなプログラムがあるのかや、経験者に聞いてほしいね!

あーちゃん:キャンパス内に冬季限定でオープンするスケートリンク。寮の目の前にあったので毎週末滑ってた⛸️
用語説明コラム
Undergraduate Research Opportunity Program (UROP): 学部生が教授や研究室の指導のもとで、実際の研究プロジェクトに参加できる制度。1年生から参加可能で、単位をもらうか給料をもらうか選択できる。
CV:アカデミアに関することに重きを置いた履歴書。
研究先を探すときに教授に送るメールの書き方が参考になるサイト
CVの書き方が参考になるサイト

なめちゃん:大学の図書館。いつ行っても、自習している学生でたくさん!テスト期間は、席を探すのが難しい。。。